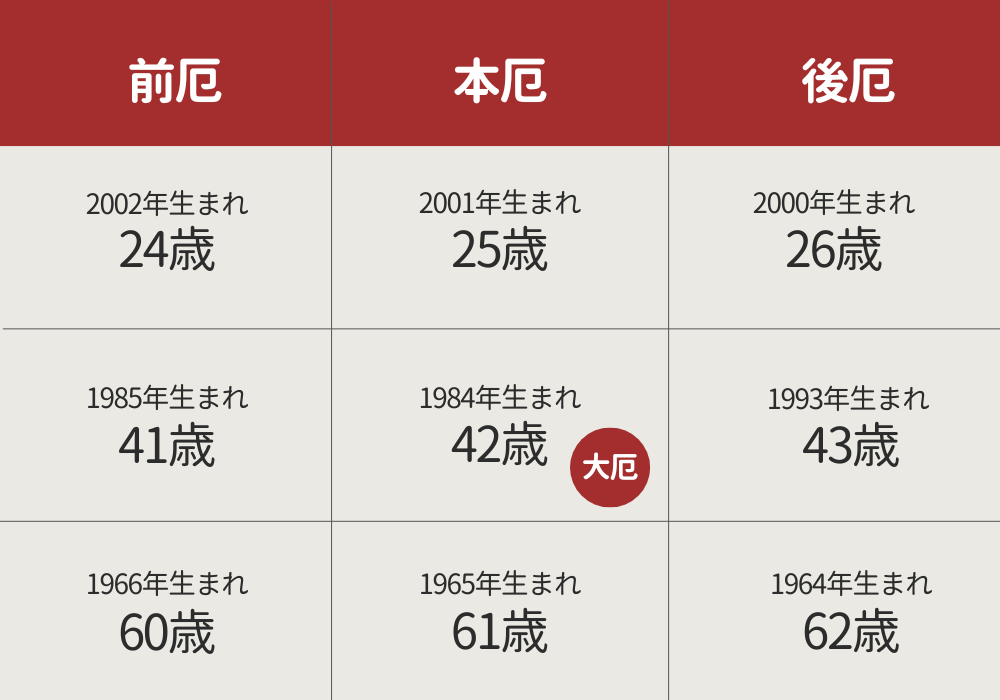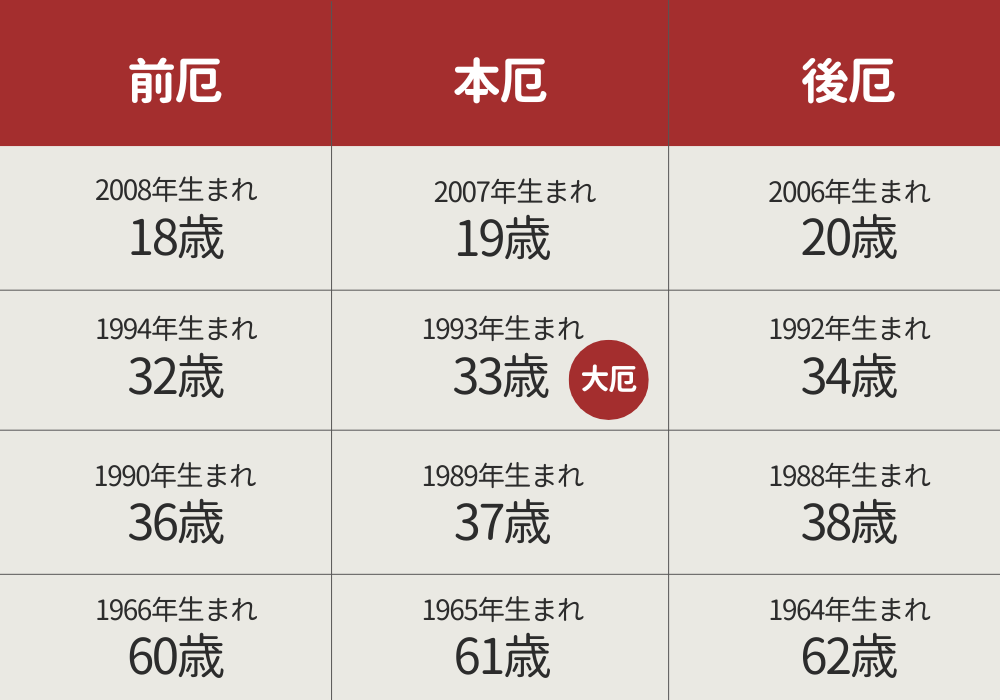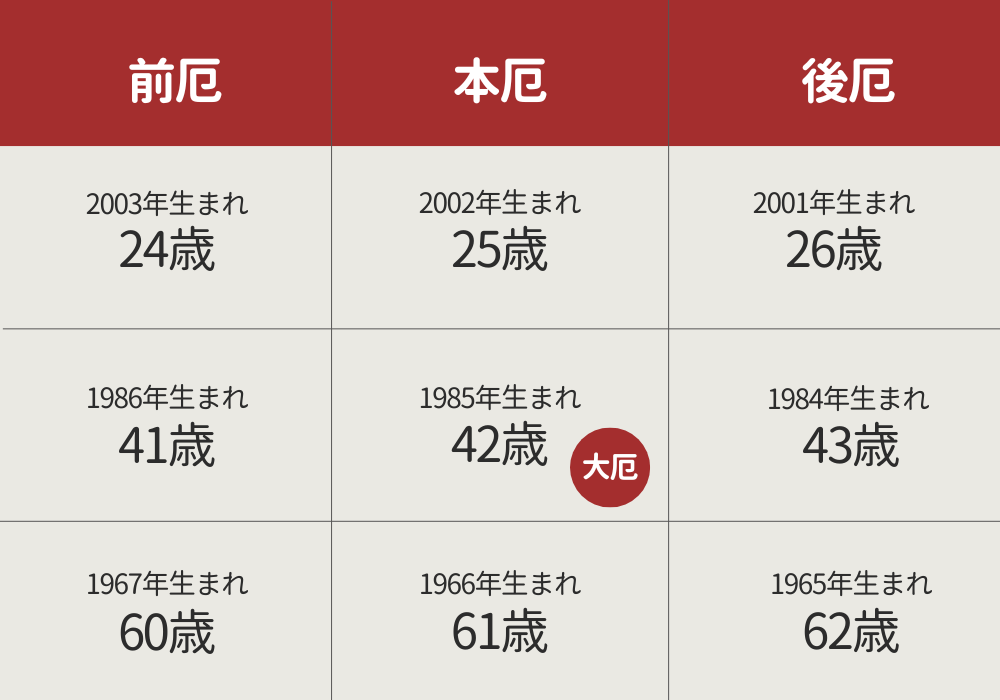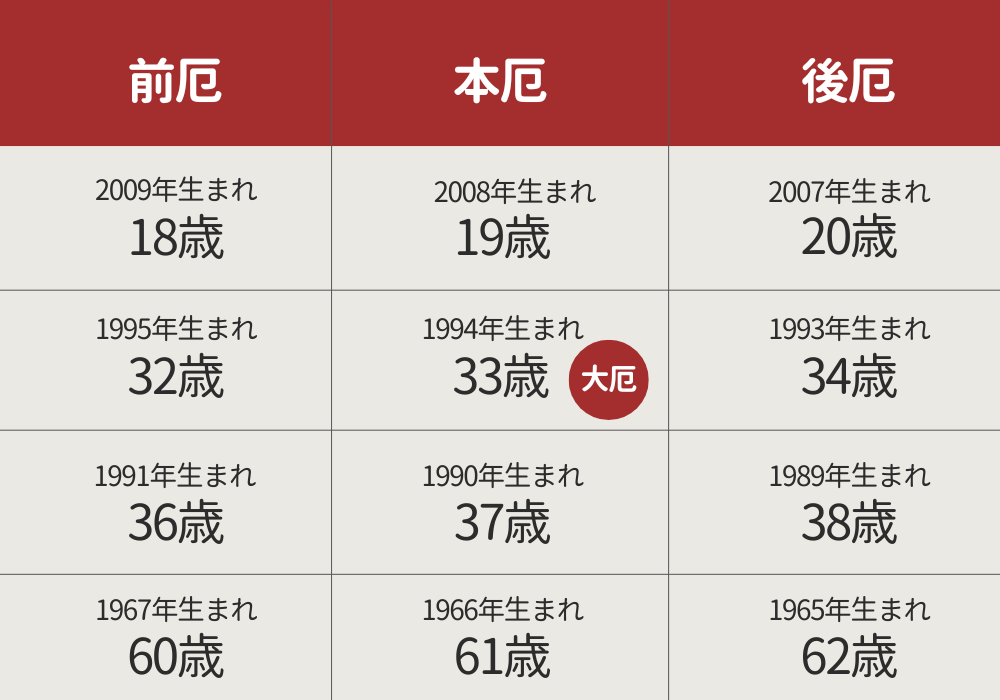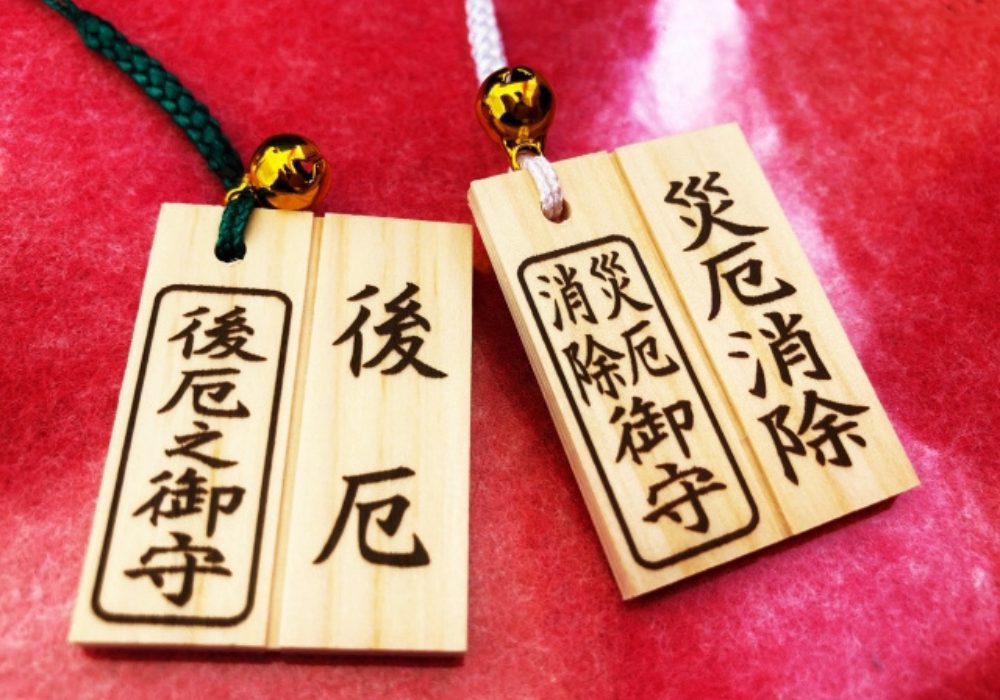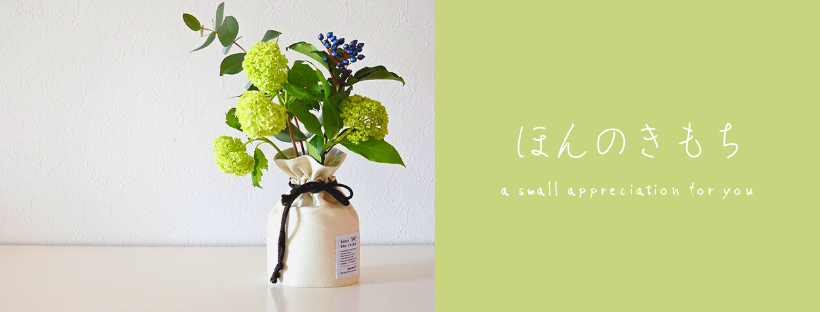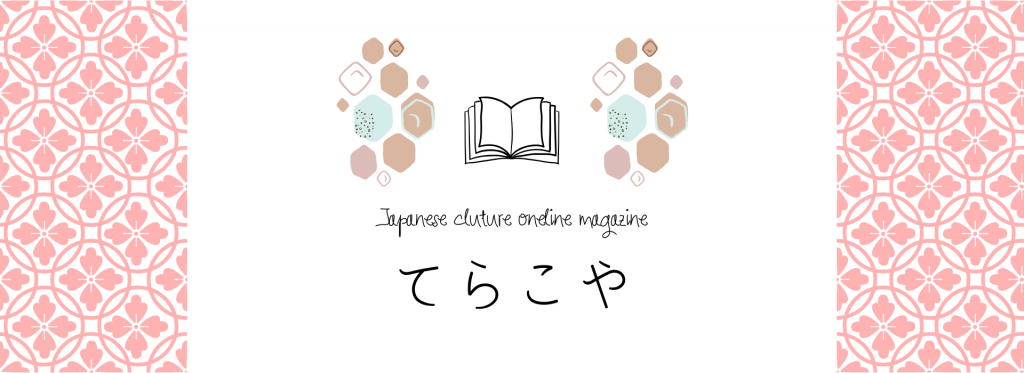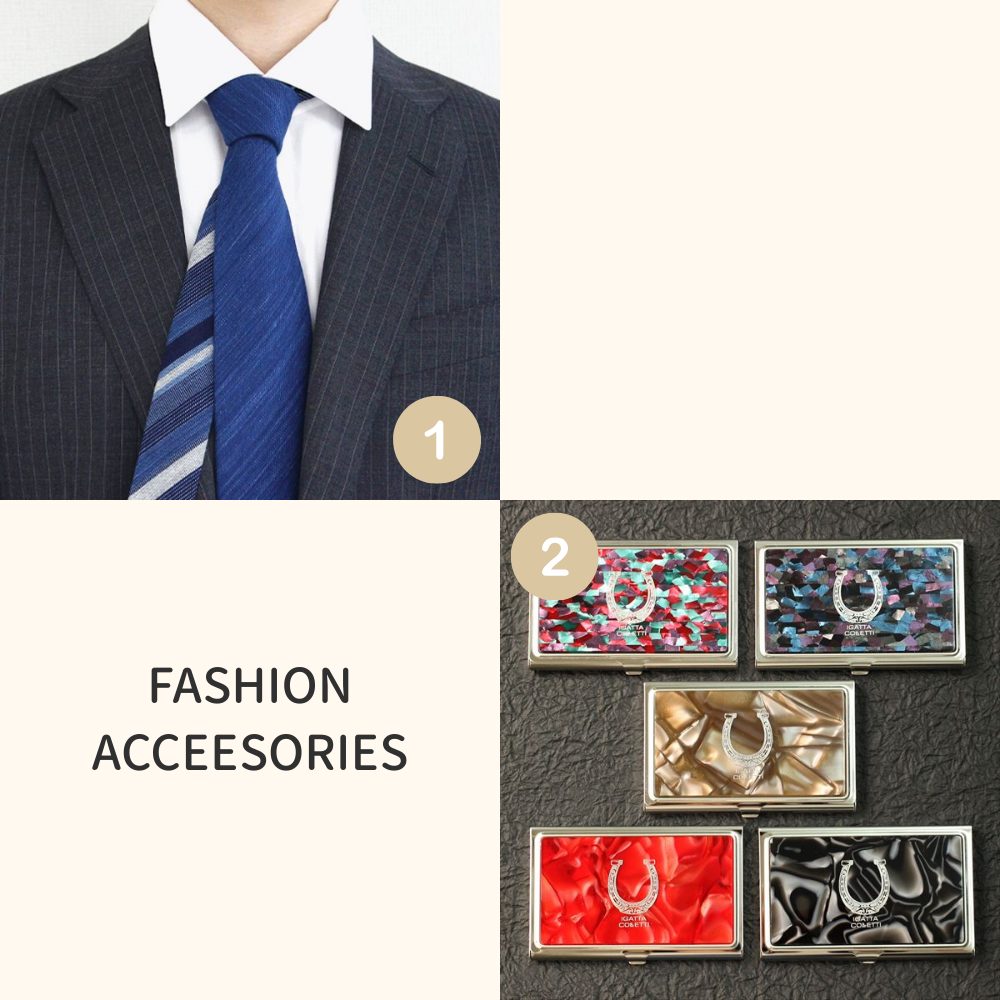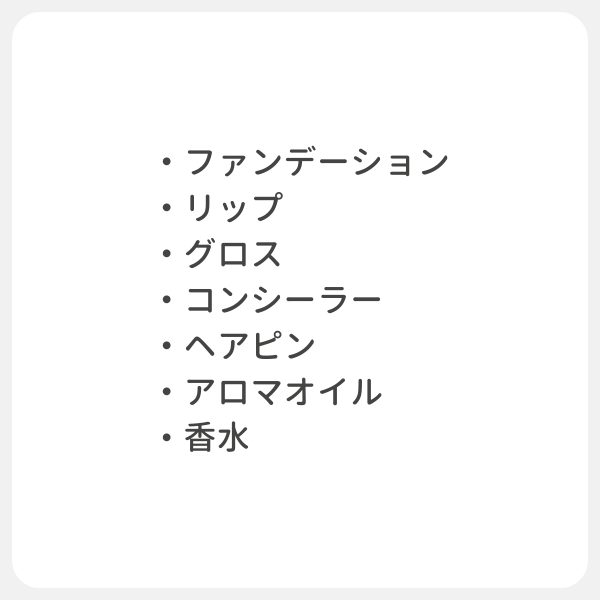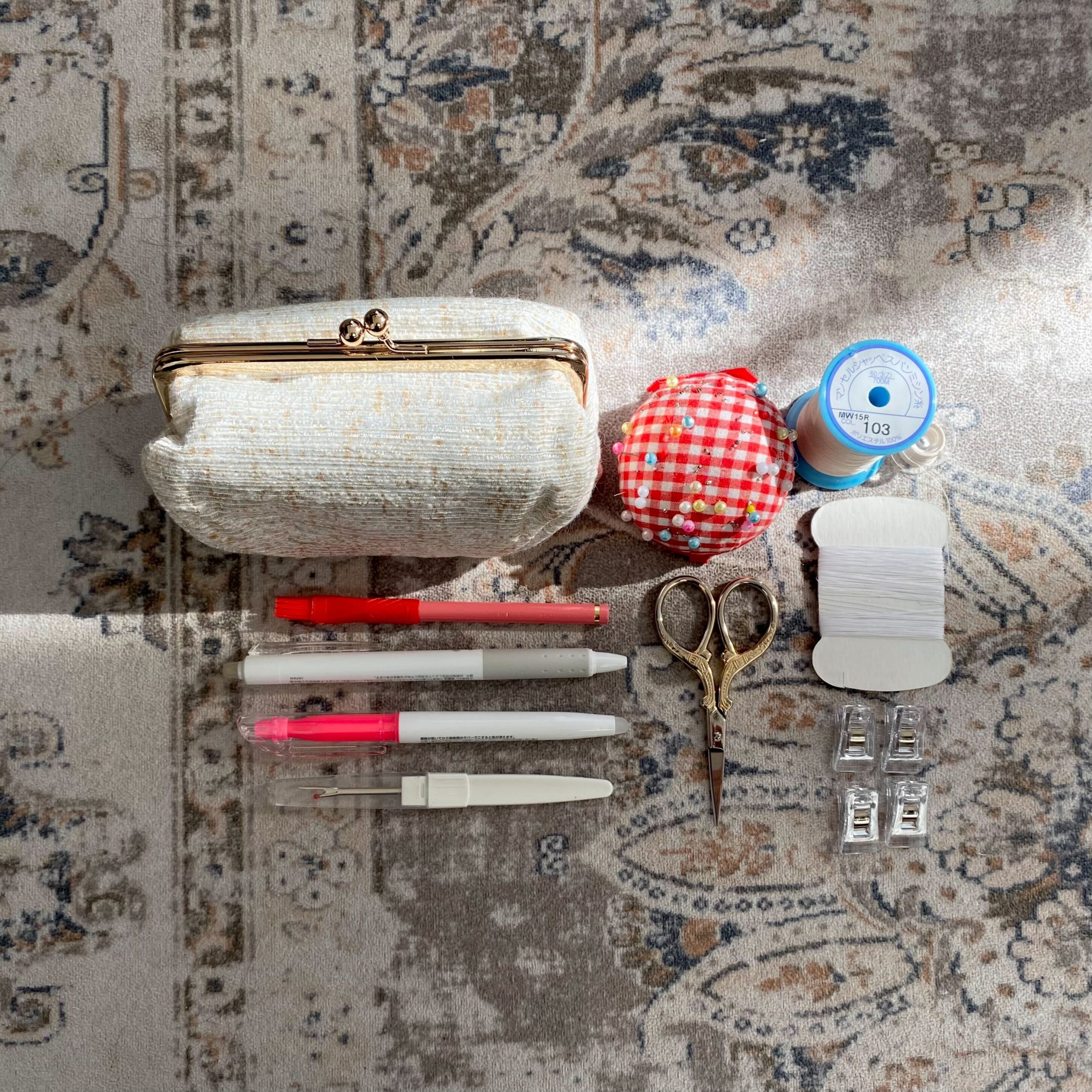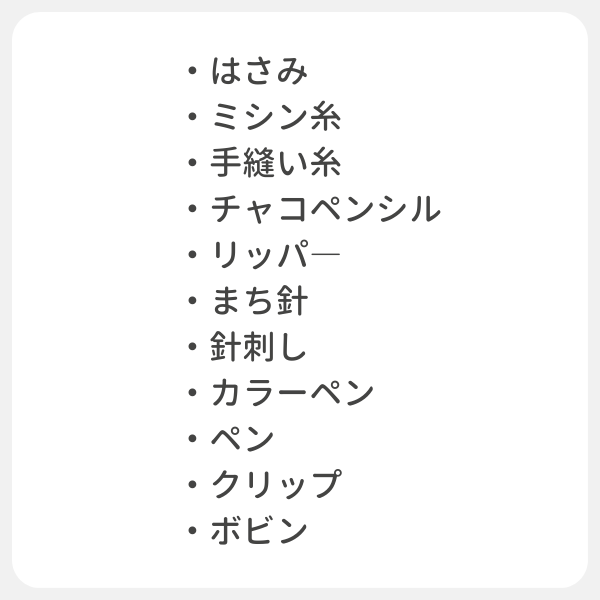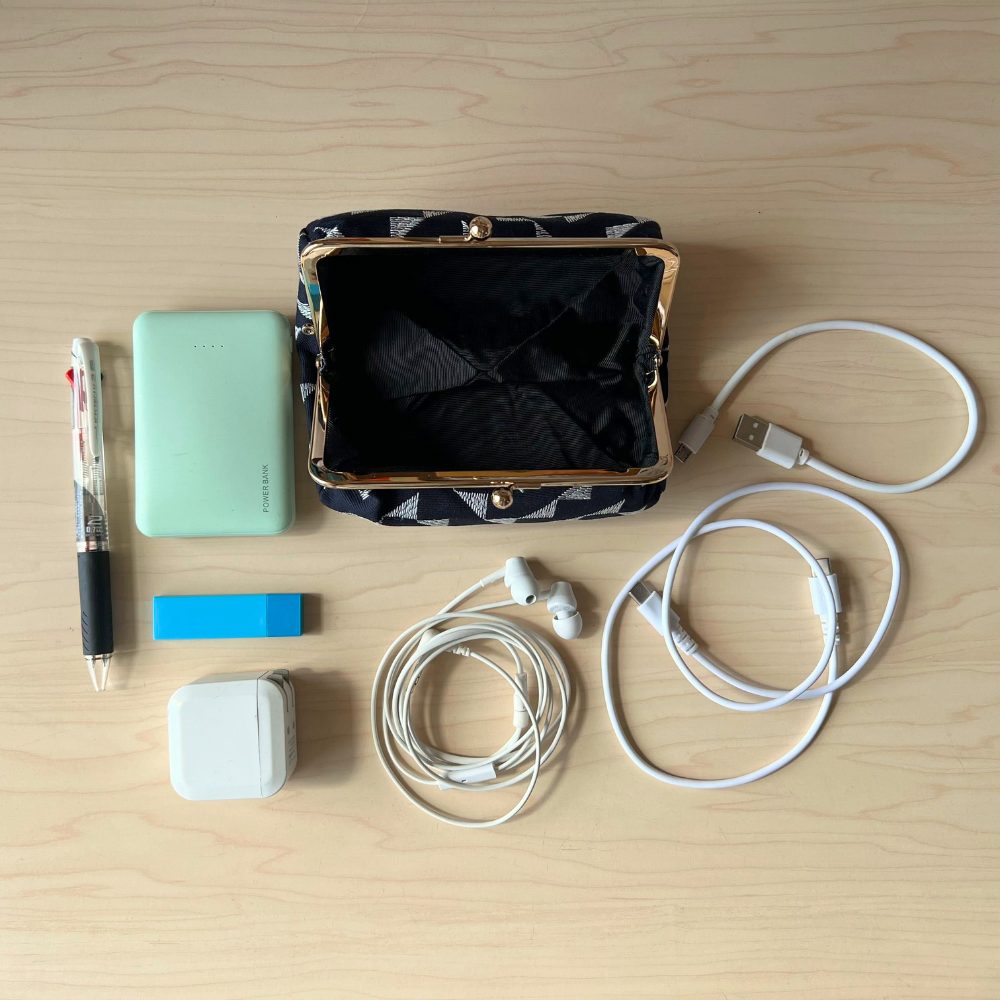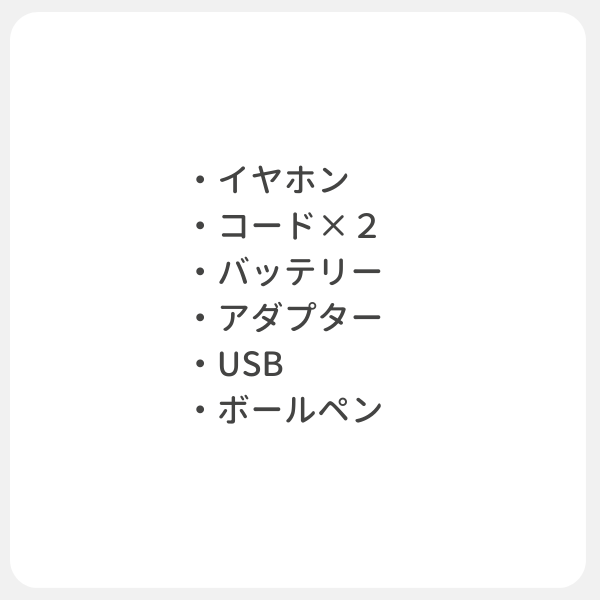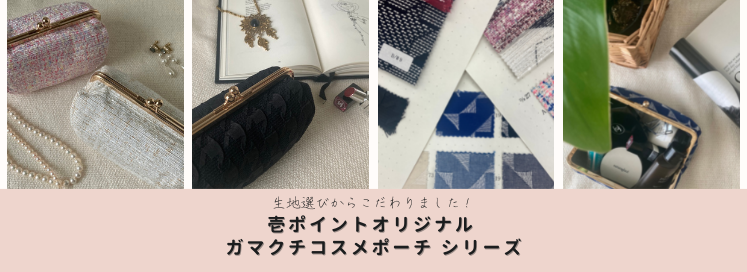近年では女性だけではなく、男性も化粧(メイク)をする機会が増えているようです。
そんな化粧をわたしたち日本人は、いつごろからするようになったのでしょうか。
この記事では、時代ごとの歴史から特徴、日本に浸透したきっかけについてご紹介します。
日本人はいつから化粧をし始めたの?|日本の化粧文化の始まり
化粧の歴史は約1,700年前といわれ、化粧の文化が古くから根付いています。
時代によっては、化粧に対する考え方が異なっていたようです。
以下では、日本の化粧文化の移り変わりを詳しく見ていきましょう。
日本の化粧文化の変遷|時代ごとに特徴を詳しく解説
ここでは、時代ごとに化粧の歴史についてご紹介します。
縄文〜古墳時代
日本で最初に「メイク」が文化として浸透したのは、縄文〜古墳時代だと考えられています。
この時代は赤色の顔料を用いて、顔や体などに模様を描いたり塗ったりしていました。
赤には魔除けの意味が込められていたようです。
当時の人にとっての化粧は、呪術のような役割があったことがうかがえます。
飛鳥〜奈良時代

飛鳥時代に入ると、遣隋使が白粉(おしろい)と紅を日本へ持ち帰ります。
『日本書紀』には中国の渡来僧である僧観成(そうかんじょう)が、「鉛白粉(なまりおしろい)」を日本で初めて作りました。
これを女性の持統天皇に献上したところ、大変喜ばれたそうです。
このころから、呪術としての意味合いが強かった赤の化粧は白へと移り変わります。
これにより「化粧=おしゃれ」と、当時の女性の化粧に対する認識も変わっていったそうです。
平安時代
平安時代に入ると白粉と紅に加え、新たなメイクが誕生します。
それが歯に墨を塗る「お歯黒」、額に描く「眉化粧」です。
当時は歯を黒くするのに、鉄漿水と五倍子粉などが使われていました。
眉化粧は生えている眉を抜き、少し上に線を引いて眉を描きます。
これが、当時の女性貴族の一般的な化粧だったようです。
また、平安時代には貴族男性の間でも化粧をするようになったといわれています。
ですが、化粧をするのは、あくまでも貴族の権威を示すものでした。
鎌倉時代
鎌倉時代に入ると鎌倉幕府が開かれ、貴族から武家の時代に変わります。
武士が新しい文化の担い手となり、少しずつ化粧も変化していきました。
白粉化粧は、鎌倉時代以降も女性たちの間で白い肌を作る定番の化粧として愛用され続けました。
安土桃山時代にかけて、白粉の用途や効果に大きな変化は見られなかったものの、白粉の種類が増加したそうです。
室町時代・安土桃山時代
室町時代から戦国時代にかけて、軽粉の生産が盛んになりました。
これにより白粉が全国で普及し、一般市民の間でも化粧が広がっていきます。
また、当時は男らしく戦う姿を連想させる武士もメイクを取り入れていたといいます。
諸説ありますが、戦場で死に際も美しくあるため、男性も化粧をしていたといわれています。
初めは権威を示していたようですが、徐々に変化していったようです。
当時、積極的にメイクを取り入れていたのは平氏です。
二大派閥である源氏は平氏との戦いで敗れたことで、平氏が権力をにぎりました。
そこで、メイクを取り入れたといわれています。
公家が行っていたようなメイクを施すことで、威厳や権力を表していたようです。
江戸時代

Supmile(サプミーレ)
モイストウォーター 120ml
江戸時代になると、武家と庶民の間に対して異なった概念を持つようになります。
武家階級の女性にとって化粧は、身分を表すもの。
当時は、白粉を厚く塗ったり、歯黒にしたりと、濃い化粧をするのが決まりでした。
一方、庶民には決まりがないため、自由に化粧をしていたといいます。
この時代は色白が美人とされていたため、薄化粧が好まれていたようです。
また、この頃からぬかを使った洗顔料や化粧水が登場し、スキンケアも本格化します。
明治時代〜現代

明治時代に入ると、化粧が急激に変化していきます。
お歯黒と眉剃りが禁止され、自分の素肌を活かした薄化粧が主流になります。
欧米からは石鹸やクリームが輸入され、少しずつ浸透していきました。
大正時代になると、働く女性が増えます。
昔では考えられなかった、短い髪の毛も増えています。
彼女たちはやがてモダンガール(モガ)と呼ばれ、当時のファッションやメイクをリードする存在でした。
出先でお直しできるよう、「棒口紅」と呼ばれるリップスティックなどが誕生しました。
さいごに

ここまで紹介してきたように、時代の変遷とともに化粧の在り方も変化していきました。
ですが、形は違えど、昔から女性が美を追求する気持ちは同じだったのではないでしょうか。
流行の移り変わりが早いなかで、次はどのような化粧文化ができるのか気になるところですね。
【関連記事】「舞妓」と「芸妓」は何が違うの?

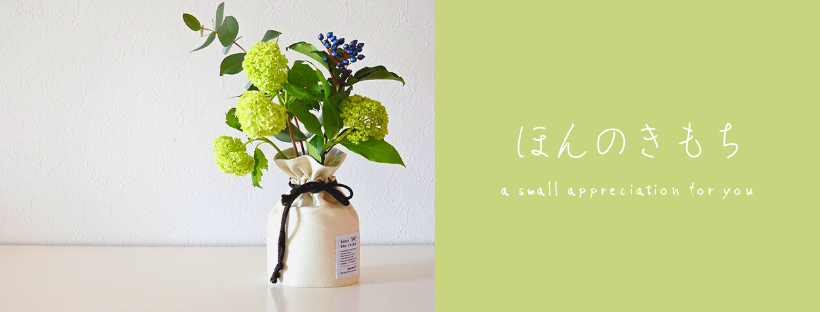
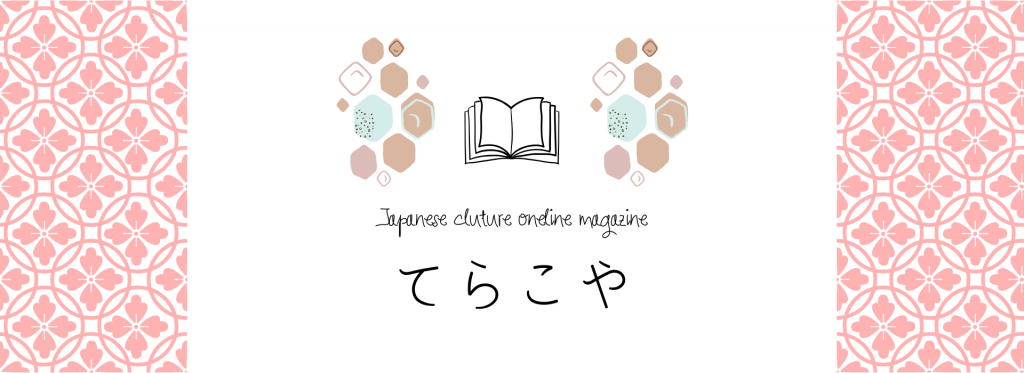
オリジナルラベルのお酒や
誕生日、結婚記念日などの
ギフト向けのお酒をご用意!
姉妹サイト「ハレハレ酒」はこちら