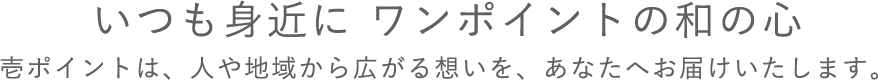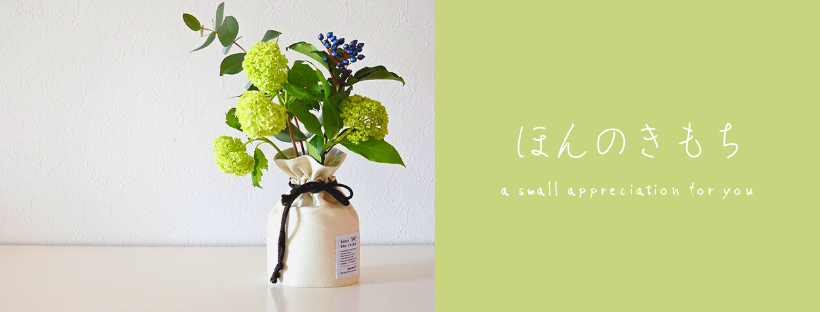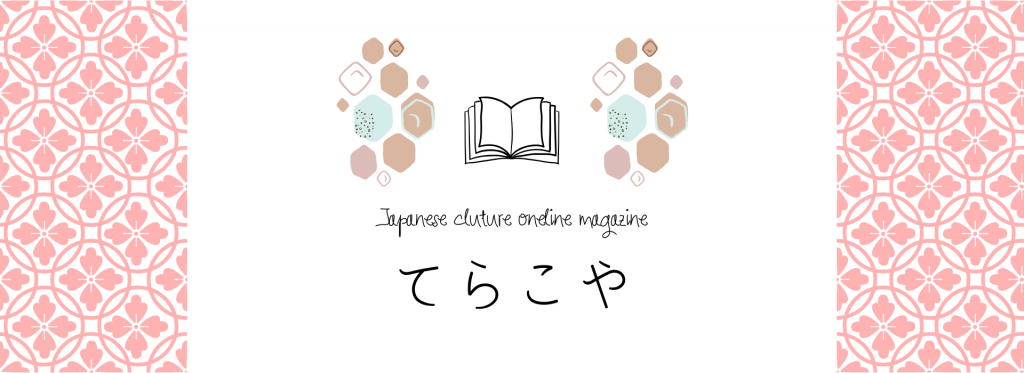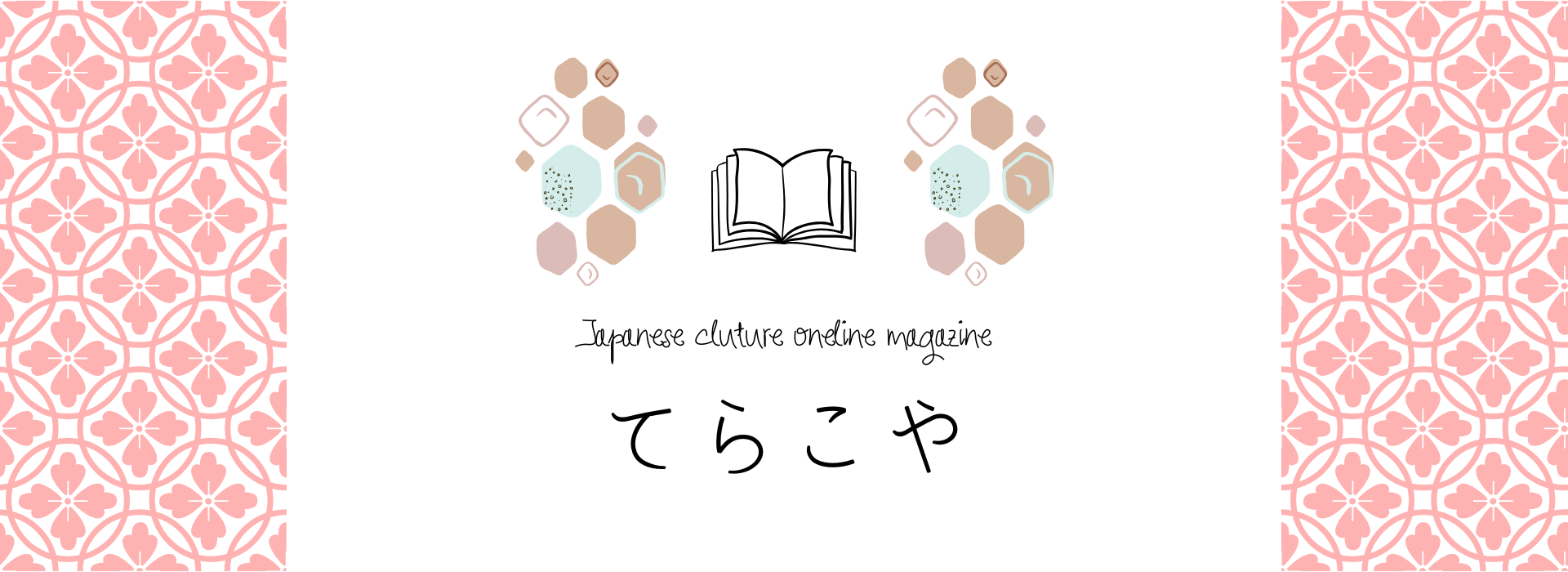水引の由来や歴史、できるまでのあれこれとは?
日本の贈りもの文化において、欠かすことができない水引。
水引は慶弔のときだけでなく、さまざまな場面で使われます。特に近年では、美しい飾りはギフトとして使うのも大活躍しています。そんな水引には、古くからの歴史と匠の技が詰まっています。
この記事では、水引の名前の由来から歴史、製造過程について詳しく紹介します。
「水引」と呼ばれるようになった由来
日本人にとって身近な水引ですが、なぜ「水引」と呼ばれるようになったのかご存知でしょうか。
諸説ありますが、なめらかで張りのある細い紐は、細長く切った和紙を縒(よ)って紐状にした紙縒(こより)に、水糊を全体に引いて乾かし固めたものです。そこから「水糊を引く」ということから、水引と呼ばれるようになったといわれています。
ほかにも、紐を染色する際、水に浸して引きながら染めたことを由来とする説もあります。
水引の歴史
水引の起源は、飛鳥時代までさかのぼります。
遣隋使として隋に派遣された小野妹子が、日本に持ち帰った贈りものが関係しています。そのとき、航海の無事を祈った紅白の麻ひもがかけられていたようです。そして、宮中への献上品や貴族間での贈答品に、紅白のひもが結ばれるようになったといわれています。のちにその素材が和紙に代わり、水引が誕生したようです。
現在、国内の水引の生産地のトップは長野県飯田市で、全国シェア約70%を誇るほか、愛媛県伊予三島市でも盛んに生産されています。
かつて、和紙の生産地の多くでは、水引も作られていましたが、近年ではごく限られた地域にとどまります。
戦後は、一般家庭でも結納や結婚式などで豪華な水引飾りが多用されました。しかし、リボンの普及にともない、水引は徐々に限られた場面でしか使われなくなってきているのが現状です。しかし、やわらかなリボンとは異なり、水引は和紙特有の張りをもち、リボンでは表現できないような凛とした美しさがあります。
ほどいてしまうと元には戻らない束の間の美もまた、水引ならではの味わいといえるでしょう。
水引の製造過程
長いテープ状に切断した和紙に水を含ませながら、数本ずつ縒っていきます。
天気のよい日や広い場所で、できあがった紙糸100本余りをひと組にして長く平らな帯状に張ります。そこへ、クレー粉や米糊、布海苔(ふのり)などを原料とした専用の糊をまんべんなく塗りながらしごいていき、しっかりと乾燥させます。白い状態のこの紙糸に、刷毛を使って赤、黄、黒などさまざまな色に染めていきます。さらに乾燥させたのち、切断したものが一般的に水引といわれる「紙巻水引」です。
また、染め分けせず金銀の紙が巻いてあるものを「金銀水引」、アルミ箔を巻き光沢を出すようにしたものを「特光水引」と呼ぶこともあります。
そのほかにも、水引に人工の絹糸を巻いた落ち着いた雰囲気のものやラメの入った細いフィルムを巻いた華やかなものなど、じつにさまざまな色合いの水引があります。芯は紙でも、さまざまな素材をまとった水引が存在します。
日常のアイテムとして溶け込む水引
近年では、お祝い事や慶事のとき、お正月のしめ縄などのほかに、水引をモチーフにしたアイテムも多く登場しています。アクセサリーからうつわなど、幅広いアイテムとして取り入れられています。
そんなアイテム1つひとつにも、意味や作り手の想いが込められています。時代の流れとともに形も変化していき、日本の伝統文化が引き継がれています。
自遊花人
箸置き -ゴールド-
水引を身近なものに
大切な人へ贈りものをする際などに、使うことが多い水引。
すこし渋いイメージもあるかもしれませんが、実はお菓子などちょっとしたプレゼントなどに、現代のライフスタイルでも気軽に使うことができます。
誕生日や差し入れのときには、蝶結びの水引をつけるなど、使う場面によって変えることで特別感も増し、もらう側もより嬉しい気持ちになるはずです。
水引にはさまざまデザインのアイテムがあるため、実際に手にとって身近に感じてみてくださいね。
オリジナルラベルのお酒や
誕生日、結婚記念日などの
ギフト向けのお酒をご用意!
姉妹サイト「ハレハレ酒」はこちら