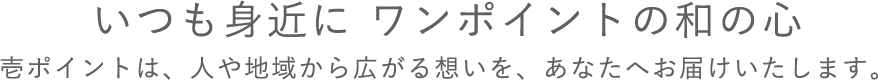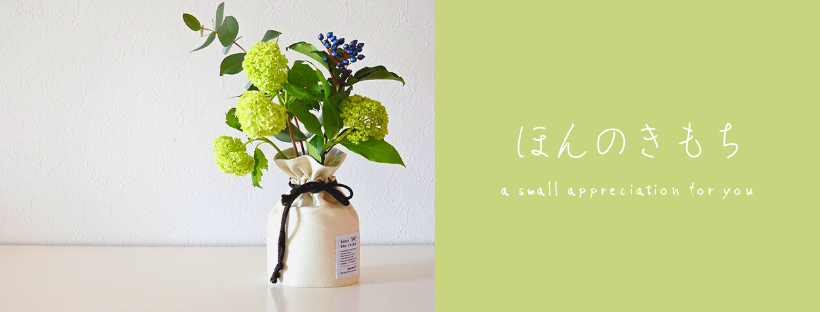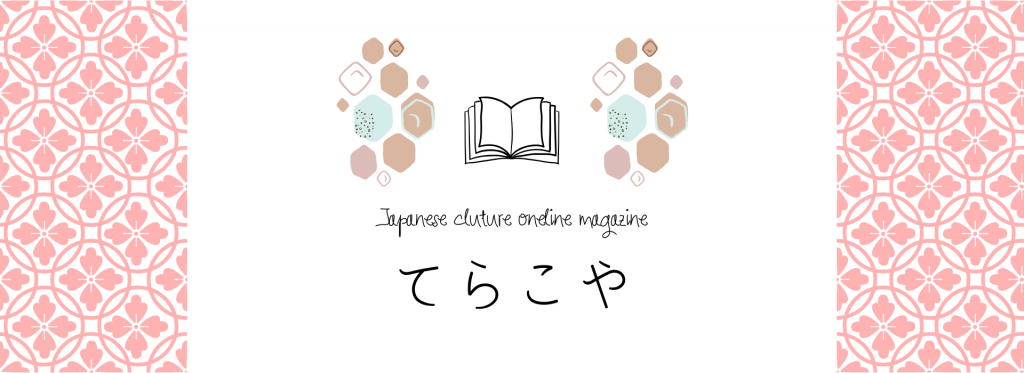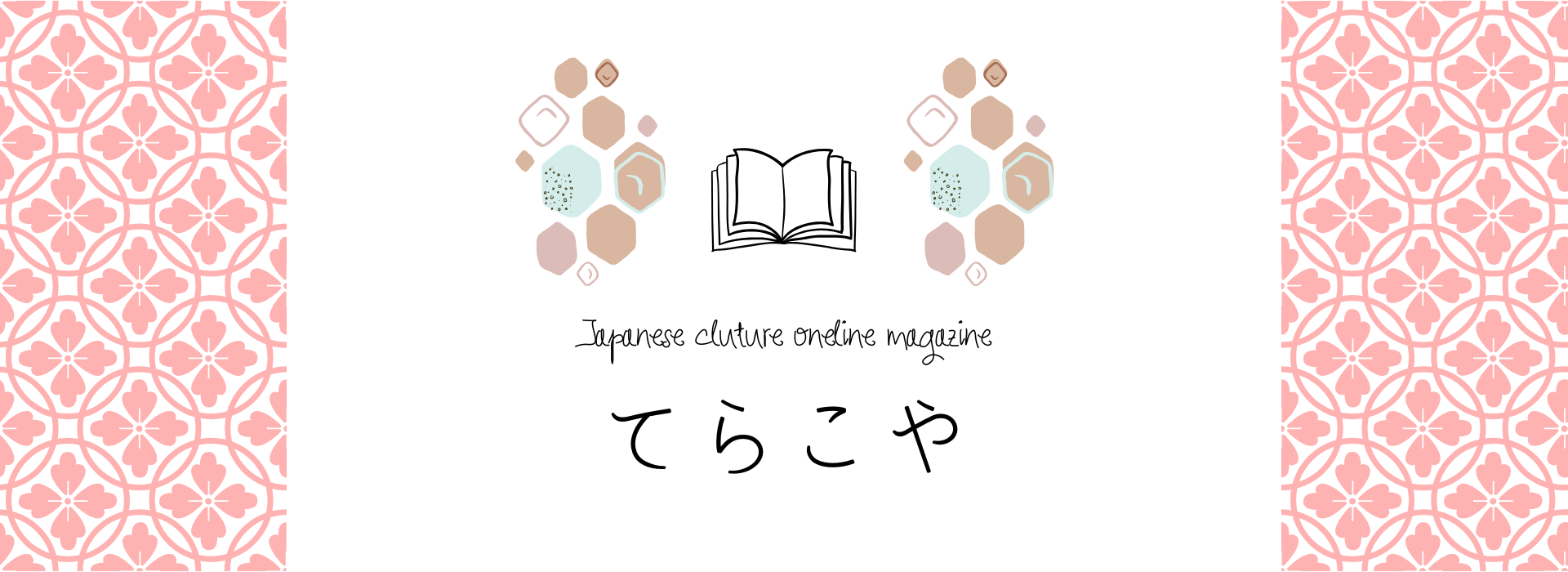幕の内弁当の「幕の内」とは?
職場や学校など、さまざまな場所で食べられているお弁当。
おかずやご飯を外に持ち運ぶことができるお弁当は、私たちの生活で欠かすことができません。持ち運びができるということから、お花見や電車旅のお供として多くの人から愛されています。
ご家庭の手作りお弁当はもちろん、コンビニエンスストアのお弁当、デパ地下で売っているお弁当など幅広い場所にあります。
そんなお弁当には、「幕の内弁当」と呼ばれるお弁当があります。
幕の内弁当はよく食べられているお弁当ですが、なぜ幕の内と呼ばれるようになったのでしょうか。
そこで今回は、幕の内弁当の歴史から由来、幕の内弁当と松花堂弁当の違いについてご紹介します。
もくじ
幕の内弁当とは、どのようなもの?
幕の内弁当とは、「俵型の握り飯と数種類の副食(おかず)を詰め合わせた弁当」のことです。
おかずは、卵焼き・かまぼこ・焼き魚・揚げ物・煮物・漬け物・佃煮など、汁気のない数種類のおかずが詰め合わせられています。
お店によっておかずは違いがあり、それぞれ工夫を凝らした料理が詰められています。
ごはんは、白米をつめるのが一般的といわれています。ご飯の上に黒胡麻が散らされ、白米が平らになった状態が多いです。本来は、俵型をしたおにぎりがつめられていたのが幕の内弁当でした。時代の流れとともにおにぎりは減っていき、ご飯の上から俵型の型押しをしたものが多くなりました。
「幕の内弁当」が生まれた歴史・由来
幕の内弁当として売られるようになったのは江戸時代の後期といわれ、「芝居文化の発展とともにうまれた弁当」として、歌舞伎と深いつながりを持っています。ここからは、幕の内弁当が生まれた由来について見ていきましょう。
「幕の内弁当」と呼ばれるようになった由来には諸説あります。
1.芝居興行のときに役者や裏方に出していた弁当をやがて観客も食べるようになり、幕間に食べる弁当だから
2.役者が幕の内(舞台裏)で食べていた弁当だから
3.芳町の「万久(まく)」という店が、小さな握り飯にお菜を添えた弁当を売り出したから
4.相撲取りの「小結(こむすび)」が幕の内力士であることになぞらえて、そう呼ばれるようになったから
5.戦国時代、戦陣の幕の内で食べた弁当だから
中でも1,2の説が有力とされていますが、「幕の内弁当と番付の幕内とは関係がない」との説もあります。
ただ、いずれにせよ、幕の内弁当は芝居小屋や相撲茶屋など江戸の庶民の娯楽につながっていたことはたしかなようです。
それぞれの仕出し弁当との違いとは?
仕出し弁当は宅配デリバリーと似ていますが、すこし異なります。宅配デリバリーは、注文をしたらすぐに届けてくれますが、仕出しは事前に注文を承っておき、予約した当日に調理したものを持っていくのが基本的です。
冠婚葬祭や会議といった、大切な場面のときに利用されることが多いです。そんな仕出しとして代表的なお弁当は、「幕の内弁当」「松花堂弁当」「折詰弁当」などがあります。それぞれの特徴、幕の内弁当との違いについてご紹介していきます。
松花堂弁当の特徴
松花堂弁当とは、内側を十字に仕切った弁当箱に料理を盛りつけたお弁当のことです。略式の懐石料理として用いられることもあり、料亭などで楽しむことができます。お弁当の中には、刺身や煮物、焼物、ごはんやお吸い物が小鉢に入れられています。このように、どこでも食べられるよう俵型おにぎりや汁気がないおかずを使用している幕の内弁当とは、大きな違いがあります。
松花堂弁当の特徴
折詰弁当とは、木でできた折箱の弁当箱の中に料理を盛りつけたお弁当のことです。隙間がないように、おかずでぎっしりと詰めているのが特徴です。また、詰めた料理の味が混ざらないように、仕切りを使った工夫が施されています。
折詰弁当の歴史は、文化7年に樋口与一という名の男性が開いていたお店「樋口屋」がきっかけになります。当時、時間がなくご飯を残していく姿を見て、竹の皮や笹で包んで持ちかえらせたのが始まりといわれています。
駅弁としても愛されている
幕の内弁当は芝居興行のときに食べられていたといわれていますが、明治時代に駅弁としても登場します。諸説ありますが、鉄道が開通して山陽線の神戸から姫路間の延伸たのをきっかけに、姫路駅で駅弁が作られたといわれています。そして、数年たった明治21年ごろに駅弁として幕の内弁当がでてきたといわれています。
現代では、新幹線など長い距離を移動する際に車内で駅弁が食べられています。景色を見ながら食事を楽しんだり、お目当ての幕の内弁当を食べたりするなど、さまざまな楽しみ方で愛されて続けています。
旅のお供としても
旅行や観劇といった、特別な日にも選ばれる幕の内弁当。日本全国、老若男女に根強い人気を誇り、長い間愛され続けています。これからお出かけや旅行を考えている方は、幕の内弁当をお供に過ごしてみてはいかがでしょうか。
【関連記事】マナーとエチケットの違い、きちんと答えられますか?