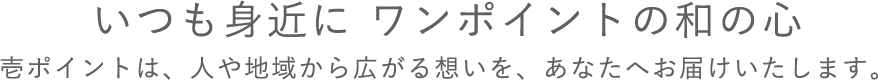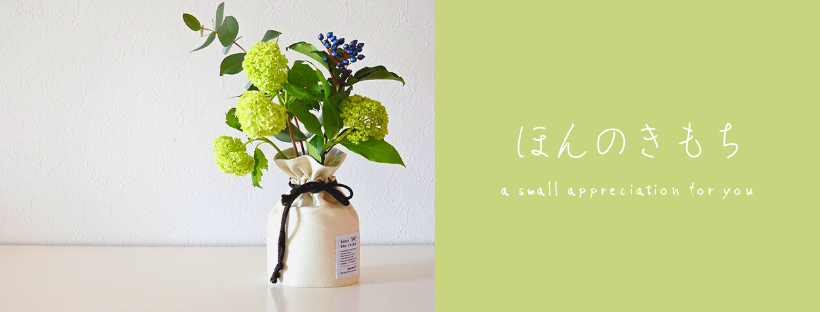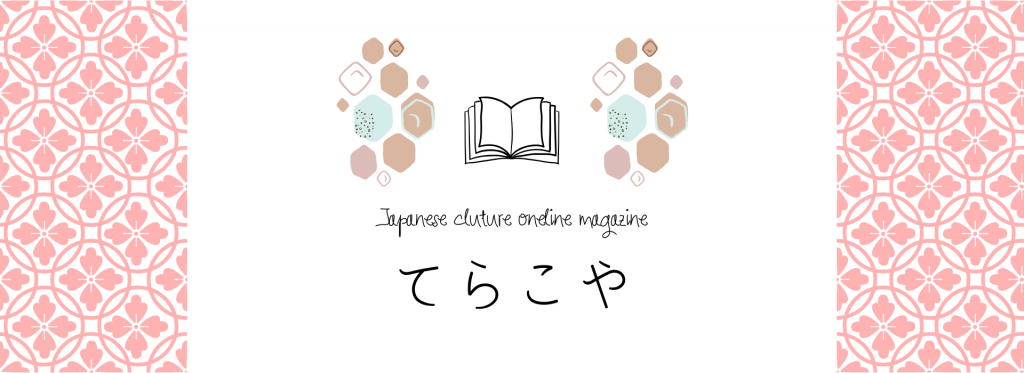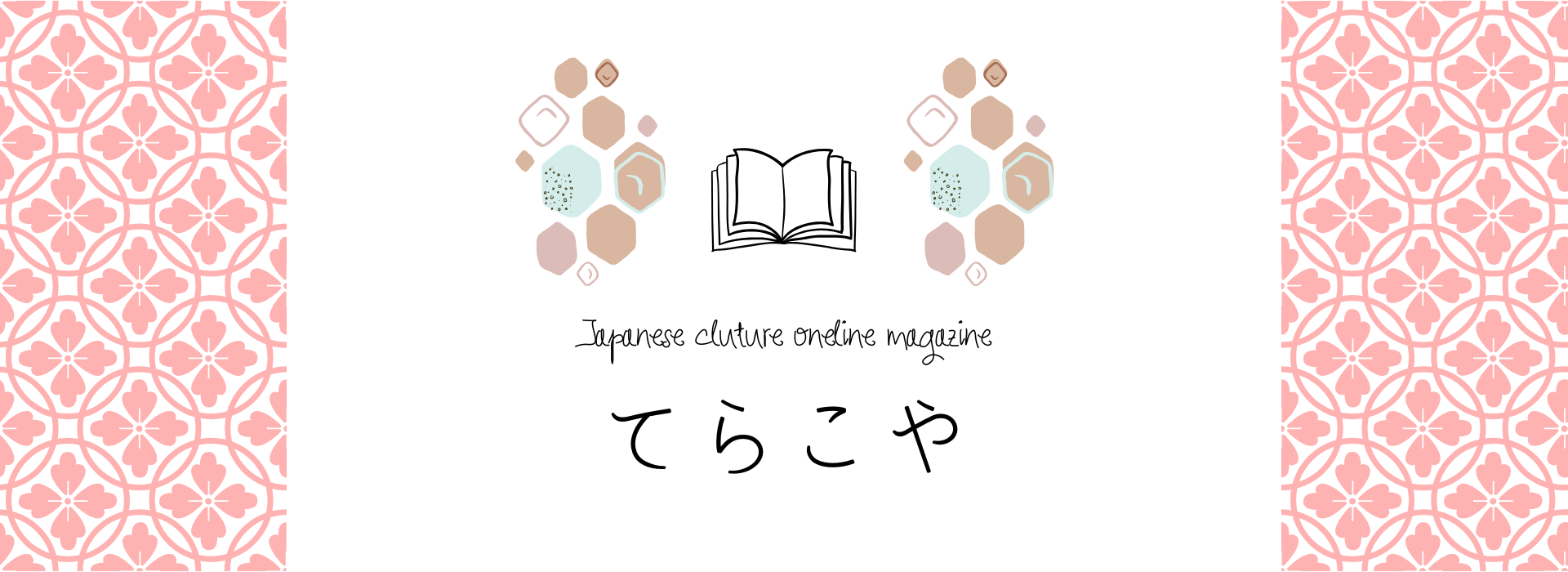読み方がやたら難しい日本の色(伝統色)②
日本の伝統的の色(伝統色)は、細やかに色分けされて種類が多いため、同様に数多く名前も存在します。
そんななかでも、すこし読み方の難しい日本の伝統的な色(伝統色)5つを引き続きご紹介します。
もくじ
あなたはいくつ答えられる? 読み方が難しい伝統色
≪海松色≫
 読み方:
読み方:
茶みを帯びた深い黄緑色は、「みるいろ」と読みます。
海松藍にまつわるエピソード:
耳にしたことがある方も多いかもしれません。
磯の岩に生える緑藻で、この色は英名のオリーブ・グリーンに一番近いとされます。江戸時代に広く流行し、「海松藍(みるあい)」「海松茶(みるちゃ)」などと派生していきました。
≪木賊色≫
 読み方:
読み方:
わずかに黒みを帯びた深い緑色は、「とくさいろ」と読みます。
木賊色にまつわるエピソード:
木賊とは多年草の常緑シダ植物で、まっすぐ竹のように伸びてゆく茎が深い緑色をしています。この茎がとても硬く、秋に刈り取って乾燥させておくと、木材や刃物を研ぐことまでできたことから、「砥草」とも書かれます。
≪楝色≫
 読み方:
読み方:
ほんのり淡く、やや青みがかった紫は、「おうちいろ」と読みます。
楝とはセンダン科の落葉高木で、古くより親しまれる栴檀(センダン)の古名です。
初夏に咲かせる淡い紫の花の色が由来となっています。
≪丁子色≫
 読み方:
読み方:
やわらかな薄茶色は、「ちょうじいろ」と読みます。
丁子色にまつわるエピソード:
平安時代からある伝統色で、開花直前に摘み取られた丁子の蕾で染めた色です。
丁子とは、生薬やお香、香辛料などにも使われる香木であるクローブのこと。東南アジア原産で、日本ではもちろん希少なものであったため殿上人にだけ使用が許されており、芳しい香りから「香色」という別名も。
≪空五倍子色≫
 読み方:
読み方:
わずかに紫がかった灰みのある焦茶色は、「うつぶしいろ」と読みます。
空五倍子色にまつわるエピソード:
ウルシ科の白膠木(ぬるで)の木の葉にヌルデノミミフシという虫が寄生する刺激で木にコブができます。このコブを付子(ふし)または五倍子(ごばいし)といい、これを砕いて煮出したタンニン酸の濃い液でこの薄墨色に染まるのです。付子は中が空洞なので、「空」の字がつきました。ちなみにこの付子や液は非常に独特なにおいがします。
平安時代の公家や武士、江戸時代の既婚女性が行っていたお歯黒の材料にも使われました。非常に独特なにおいがする素材のはずなのですが…。
のちに臭くない黒染めの素も作りだされ、こちらは高級なお歯黒として御所やお金持ちの家で使われたようです。
知れば知るほど面白い、読み方が難しい伝統色たち
 Kaguyahime
Kaguyahime
豆花火 -豆皿-
記事を通して、日本の伝統色の読み方を楽しんでいただけましたか?
難しい日本の伝統色はまだまだたくさん存在します。
今回の記事をきっかけに興味をもっていただけたら幸いです。