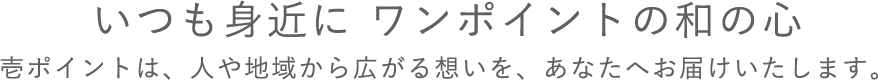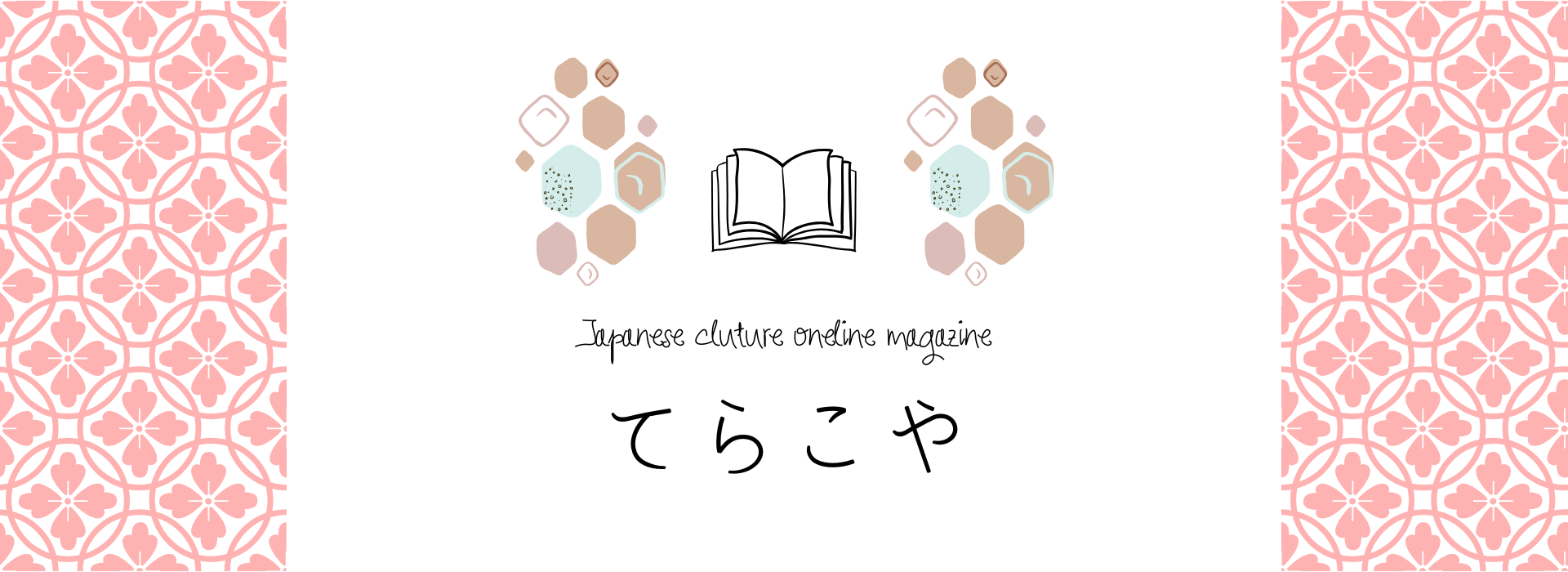お彼岸の季節に思い出したい、《六波羅蜜》って?
お彼岸になると、「六波羅蜜」という言葉を聞くことがあるかもしれません。
六波羅蜜は、仏教の世界においてとても大切な6つの修行のこと。すこし難しそうに聞こえる言葉ですが、人々の暮らしにおいて大切なことです。
この記事では、六波羅蜜にどのような修行なのか、わたしたちの暮らしに取り入れる際の実践方法についてご紹介します。
もくじ
お彼岸の意味と悟りの世界
彼岸という呼びかたは、サンスクリット語の「パーラミター(波羅蜜多)」を訳した「到彼岸」を略したことに由来するとされています。
到彼岸とは「あちらの岸(あの世)」のこと、つまり悟りの世界である極楽浄土だと信じられてきました。
それに対し、私たちが日々を過ごしている「こちら側(この世)」には迷いや苦悩に満ちあふれている世界だとされてきました。そのため、極楽浄土に行くために、迷いや苦悩を断ち切るためには仏教世界の「六波羅蜜」という教えを実践して、悟りを開くことが必要だと説かれています。
仏教における「六波羅蜜」の位置付け
六波羅蜜(ろくはらみつ)とは、仏様の境地に至るためにこの世で行う修行のことです。お彼岸はこの世とあの世が近くなり、悟りの世界である極楽浄土が近くなるため修行期間とされています。
そもそも六波羅蜜とは、菩薩(ぼさつ)が悟りを求めて行う仏道です。そのため仏教の世界では、お彼岸に限らず日々の生活で大切な教えであるとされています。
仏教における六波羅蜜って、どんなもの?
それでは、仏教における六波羅蜜とはどのようなものなのでしょうか。
「六波羅蜜」ということばの意味・語源
六波羅蜜(ろくはらみつ)とは、仏様の境地に至るためにこの世で行う6つの修行のことです。
六波羅蜜の語源は、サンスクリット語のparamita(パーラミタ)からきているといわれています。
6つある波羅蜜の意味とは
| 六波羅蜜 | 意味 |
| 「布施」(ふせ) | 財や心を周囲の人へ施すこと |
| 「持戒」(じかい) | 心を戒めること、周囲の人へ迷惑をかけないこと |
| 「忍辱」(にんにく) | 愚痴や不平不満をもらさないこと、腹を立てないこと |
| 「精進」(しょうじん) | 常に全力で物事にとり組むこと、努力をおしまないこと |
| 「禅定」(ぜんじょう) | 心を静かに保ち、日ごろの言動を省みるひと時を忘れないこと |
| 「智慧」(ちえ) | 真実を見る智慧、そして正しい判断力を身につけること |
六波羅蜜と八正道の違い
六波羅蜜は、悟りの世界に行くために行う6つの修行のことです。それに対して八正道(はっしょうどう)は、修行ではなく8つの正しい道を示しています。具体的には、その人から煩悩が消え去り、安らかな状態である涅槃の境地になることです。
| 八正道 | 意味 |
| 正見(しょうけん) | 正しく見ること |
| 正思惟(しょうしゆい) | 正しく思うこと |
| 正語(しょうご) | 正しい言葉を使うこと |
| 正業(しょうごう) | 正しい行動をすること |
| 正命(しょうみょう) | 正しい生活を送ること |
| 正精進(しょうしょうじん) | 正しく努力すること |
| 正念(しょうねん) | 心が乱されない状態のこと |
| 正定(しょうじょう) | 精神統一させ、心を安定させていること |
日々の暮らしに取り入れたい、六波羅蜜の実践方法
六波羅蜜はお彼岸の中日以外の6日間、布施から順番に修行を行います。具体的には供物を供えたり、お花を供えたりして過ごします。
六波羅蜜はお彼岸にするものとされていますが、日常生活でもぜひ意識したいものです。ここでは、どのようなことが実践できるのかご紹介します。
布施(ふせ)
布施とは人やすべての出来事に対して、手を差し伸べることができることです。このような行いを布施行と呼び、3つの布施行に分けられます。
| 布施 | 意味 |
| 財施(ざいせ) | 人に金銭や物を施すこと |
| 法施(ほうせ) | 知識を元に教えを説くこと |
| 無畏施(むいせ) | 人々の不安や恐怖を取り除くこと |
持戒(じかい)
持戒とは文字どおり戒めをもったり、自分でルールを決めたりすることです。具体的には、「殺生をしてはいけない」「盗みをしてはいけない」などといったルールを決め、それらを日々の生活で心がけながら過ごすようにします。
忍辱(にんにく)
忍辱とは、周囲からどのようなことを言われたり、残念な結果が起きたりしても、負けないように強い心で耐えることです。普段ちょっとしたことで感情的になってしまう方も、日ごろから謙虚に受け止めるよう意識していくことが大切です。
精進(しょうじん)
精進とは継続的かつ、努力を惜しまないことです。自分の決めた目標に向かって、努力し続ける大切さが必要です。たとえば、仕事や勉強などで目標設定をして実践するのがよいでしょう。まずは小さな目標からでも始めてみて、精進を意識することが大切です。
禅定(ぜんじょう)
禅定とは、どのようなことが起きても、落ち着いた心をもつことです。何事にも冷静対処できるようになるには、日ごろの心がけが大切です。例えば、1人で落ち着いた場所で心を静かに保つ修行をします。感情的になることがあっても、一度冷静になり自身を客観的に見ることを意識しましょう。
智慧(ちえ)
智慧とは知恵と異なり、真実を正しく見ること、正しい判断力を身につけることです。本や新聞から情報を得たり、何かの問題に疑問を抱いたりと、日常生活で物事が正しく考えられているかどうか意識づけることが重要です。
さいごに
難しそうに聞こえて、意外と日常生活でも取り入れやすい修行「六波羅蜜」。
六波羅蜜の考え方は、人々を成長させてくれるものです。修行で身につけた力は、必ず心の糧となるでしょう。
日々の暮らしではもちろんのこと、お彼岸ではご先祖様に感謝の気持ちを込めて六波羅蜜を実践してみてくださいね。