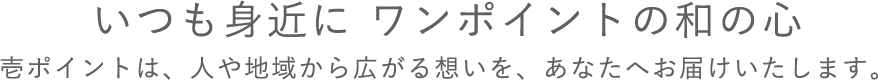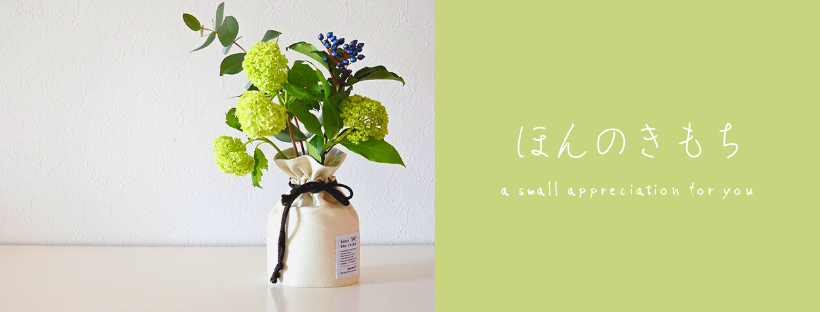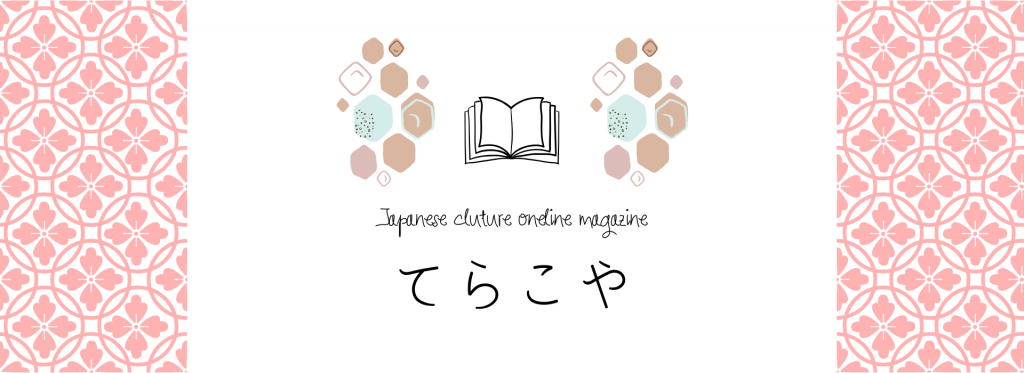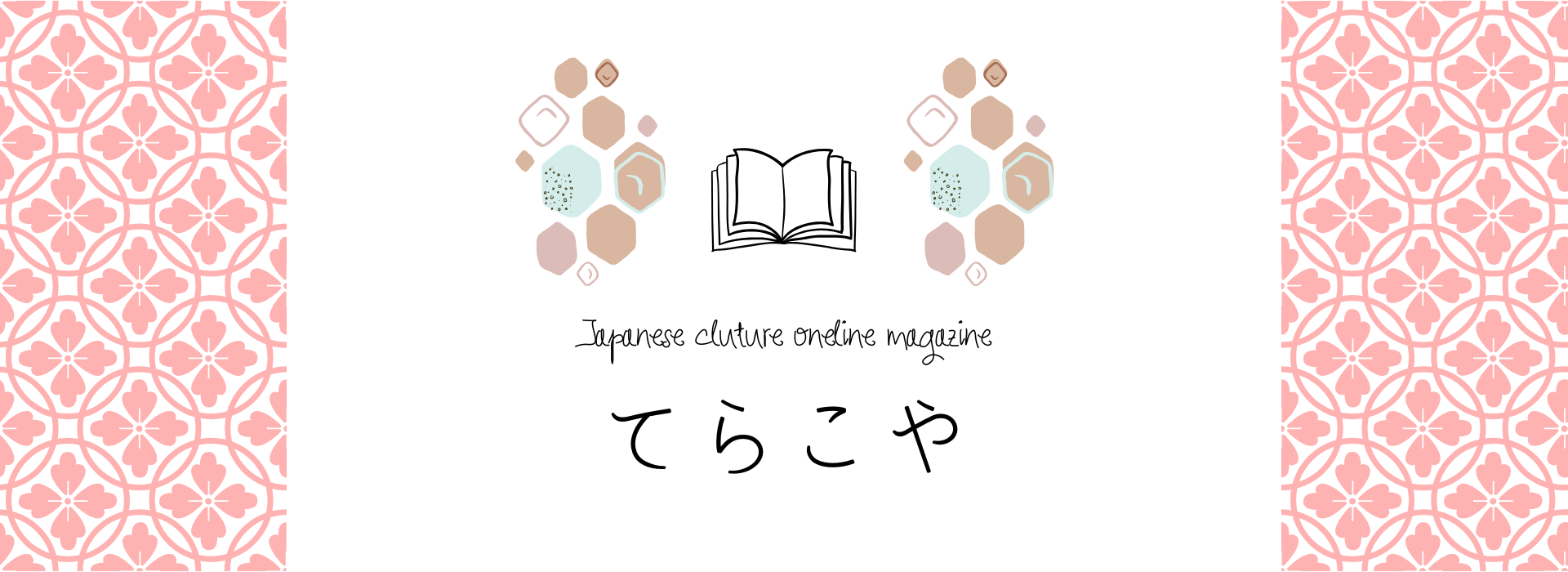こどもの日の由来・歴史、端午の節句との違いって?
毎年5月5日は、子どもの成長と健康を願うこどもの日(端午の節句)。
こどもの日が近くなると、さまざまな場所で鯉のぼりを目にする機会が増えます。
この日は兜(かぶと)を飾ったり、ちらし寿司などを食べたりして過ごすのが一般的。
子どもたちにとってお祝いの日でもありますが、お母さんにとっても大切な日なのをご存知でしょうか。
この記事では、こどもの日の由来や歴史から端午の節句との違い、過ごし方についてご紹介しきます。
もくじ
こどもの日はどのような日?
こどもの日はこどもの成長を願う日と共に、母親お母さんに感謝をする日です。
また、五節句のひとつである端午の節句でもあります。
では、こどもの日と端午の節句はどのよう違いがあるのでしょうか。
こどもの日とは?いつ?
こどもの日(端午の節句)は、毎年5月5日です。
この日は国民の祝日であり、ゴールデンウィーク期間中でもあります。
冒頭でも少しふれたをおり、こどもの日はこども達の成長を願う日であり、母親に感謝をする日です。
国民の祝日に関する法律によると、「こどもの人格を重んじ、こどもの幸福をはかるとともに、母に感謝する」と記載されています(祝日法)。
端午の節句との違いは?
こどもの日は、男の子と女の子すべての子どもをお祝いする日です。
しかし、端午の節句は男の子の誕生と成長を祝い、健康を願います。
こどもの日は国民の祝日であり、端午の節句は日本の伝統行事という点も大きな違いです。
こどもの日の由来・歴史
アデリア
つよいこグラスnico S&M セット
もともと5月5日は、男の子の健やかな成長を願う「端午の節会(せちえ)」とされていました。
しかし、後にこどもの日として浸透していきます。
端午の節句の起源
端午の節句の起源は、中国からきた風習といわれています。
中国では災いや邪気を祓うため、菖蒲(しょうぶ)を使った行事が行われていました。
古来より中国では、菖蒲が邪気を祓う縁起のよいものとして知られています。
また、奇数が重なるのは縁起がよい日とされ、5月5日には菖蒲湯に入ったり、菖蒲の飲みものを飲んだりしていました。
このような風習が奈良時代に日本へ伝わり、「端午の節会(せちえ)」という名で定着していったようです。
江戸時代には、男の子が生まれた際に家紋が描かれたのぼりを立て、誕生を知らせるなど男の子が主役の行事でした。
こどもの日の由来
端午の節句だった5月5日は、祝日法により1948年に「こどもたちの人格を重んじ、幸福をはかるとともに、母に感謝する日」とされ、こどもの日が制定されました。
男の子だけの日とされていましたが、性別関係なくすべての子どもが対象の日となります。
ちなみに、毎年11月20日は「世界こどもの日」です。
1954年11月20日に、国際連合総会によって制定されました。
何をして過ごす?
こどもの日は子どもの成長を願う日ですが、具体的にどのようなことをして過ごすのか見ていきましょう。
鯉のぼり(こいのぼり)
鯉のぼりを飾るようになったのは、江戸時代の風習からきているといわれています。
当時武家で男の子が生まれたとき、家紋が描かれたのぼりを立てて誕生を知らせていました。
また、中国には登竜門と呼ばれる「滝を登った鯉が竜になる」という伝説があります。
その伝説をもとに、こどもの立身出世や成長を願い鯉のぼりが飾られるようになったようです。
五月人形
こどもの日には鯉のぼりのほかに、欠かせないのが五月人形。
五月人形とは、「鎧飾り」「兜飾り」「武者人形」の人形などのことです。
人形を飾るのには、災厄や事故から守り、男の子の健康と成長を願うといった意味が込められています。
また、兜や弓などの装備をまとった人形を飾るのは、子どもを守ってくれるようにといった願いも込められています。
五月人形は、飾ってから片付けるまでの注意が必要です。
一般的には、5月中旬から5月下旬頃までには片付けをしたほうがよいといわれています。
5月を過ぎると梅雨の時期に入るため、カビを防ぐためにも湿気の少ない日が適しているようです。
しかし雛人形と違い、この日までに片付けなくてはいけないといった決まりはありません。
そのため、ご家庭によって片付けるタイミングも決めても問題ありません。
こどもの日にいただく行事食とは
こどもの日は五月人形や鯉のぼりのほかに、行事食を用意してお祝いする家庭もあります。
当日は、どのようなものが食べられているのか見ていきましょう。
柏餅(かしわもち)
柏餅とは、柏の葉で餡の入ったお餅を包んだ食べものです。
新芽が出るまでの間に古い葉が落ちないことから、家系が途切れることなく子孫繫栄などを意味します。
そのため、関東では縁起のよい食べものとして食べられています。
ちまき
ちまきとは、もち米やうるち米を使った皮の中にさまざまな具材を混ぜて、笹の葉や竹の皮で包んだ食べものです。
ちまきが縁起のよい食べものとされた起源は、中国の出来事に由来しています。
5月5日に屈原(くつげん)と呼ばれる忠誠心の高い中国の政治家が、川へ飛び込み亡くなりました。
その際に、供養として多くの人々がちまきを川に投げんだといわれています。
そこから、ちまきを食べることで真が強く忠誠心の強いこどもが育つという言い伝えができたようです。
その言い伝えが日本にもやってきて、5月5日に関西ではちまきが食べられるようになりました。
カツオ(鰹)
カツオには、強い男の子に成長して欲しいといった願いが込められています。
カツオは「勝つ男」と読む語呂合わせからきており、縁起がよい食べものです。
そのため、端午の節句の日に食べられるようになったといわれています。
ちらし寿司
こどもの日に限らず、お祝いの席でよく食べられているちらし寿司。
具材には海老や蓮根など、縁起のよいとされている食材が入っています。
色も鮮やかで食卓を一気に華やかにしてくれるため、こどもの日にもぴったりな料理です。
日本の伝統的な行事
5月5日はこどもの成長を願いお祝いをしますが、じつはお母さんに感謝をする日。
また、柏餅を食べたり菖蒲風呂に入ったりと、日本の伝統的な行事でもあります。
こどもにとって、たくさんのことが経験できる素敵な日です。
ぜひ、行事食を用意してお祝いを楽しんでくださいね。
オリジナルラベルのお酒や
誕生日、結婚記念日などの
ギフト向けのお酒をご用意!
姉妹サイト「ハレハレ酒」はこちら